
あなたがブレイクダンスを始めた、興味を持って見るようになったのはいつ頃でしょうか?
中にはここ最近という人や、数年前からという人もいるのではないでしょうか?
現在のブレイキンシーンでは当たり前になって定着しているようなことも、実はここ最近で一般的になってきた、変わってきたことも少なくありません。
この記事では、ブレイキンが日本に入ってきてから、まだ世の中的にもあまり認知がされていなかったマイノリティーな時代、2000年以前の黎明期と2025年現在のブレイキンを取り巻く環境を比較して、大きく変わってきたと言える変化10選について紹介します!!
その1:認知度・社会的地位の向上

2024年、ブレイキンが正式なオリンピック種目として初めて採用されたというブレイキンのシーンにおいて歴史的な出来事が起きています。パリオリンピックを通して初めてブレイキンというものを知ったという人も少なくないのではないでしょうか。これまであまりブレイキンのことを知らなかった人からすると、今回の正式種目としての採用も「そうなんだ。へー、凄いね。」という程度の人もいるかもしれません。
しかし、ブレイクダンスがオリンピックの種目に採用されるなんてことは、以前は考えられもしなかったことであり、そんな発想自体がなかったのが一般的なブレイキンシーンの考え方だったのではないかと思います。(そのため、オリンピック種目としての採用が決まった際には、賛否両論の様々な意見が飛び交いました。)
SNSだけに留まらず、テレビなどのマスメディアでも連日ブレイキンのことが取り上げられ、地上波でもリアルタイムで放送されたことで、ブレイキンの認知度も世界的に飛躍し、一定の社会的地位も得たと言っても過言ではないかと思います!!
パリオリンピック日本代表のSHIGEKIXは、企業のスポンサーもいくつも付いており、CMや屋外広告などでの露出も多く、ブレイキンをしていない一般の人にまでその名前が知れ渡るほどの知名度となっています。
これまでは、たとえ大きな国際大会で優勝したとしても、Bboy、Bgirlの中での知名度は上がっても一般の人に知られるということは、ほぼほぼ無かったと言ってもよいのではないかと思います。
また、日本で唯一のプロダンスリーグであるDリーグでのKOSE 8ROCKSや、ブレイクダンス×オタクという切り口でその界隈では圧倒的な人気を誇るリアルアキバボーズ、人気Youtuberのフィッシャーズに所属するザカオなど、Bboy、Bgirlの活躍の場が広がっており、こうしたところをきっかけにブレイクダンスを知った、始めたという人も増えてきています。
こうした知名度のあるBboy、Bgirlには特定のファンもつき、半分タレントのようになってきています。
日本でも企業が特定のBboy、Bgirl、Crewのスポンサーになることも増えてきており、ブレイキンのイベントを開催、協賛することも増えてきています。
とても昔では考えられなかったことですが、今後もこの流れが継続、拡大していって欲しいですね。
その2:技術面、スキル面の爆発的な進化・底上げ

まずは何と言っても技術面、スキル面の爆発的な進化・底上げがなされたことでしょう!!
当時でも世界トップレベルのBboyは素晴らしい技術、スキルを持っていたことは確かですが、まだまだ世界的に見ると全体のレベルは今ほど高くはありませんでした。
それがこの20年~30年ほどで、急激に高度化、複雑化したムーブを使いこなすBboy、Bgirlが世界的に増えたことが挙げられるかと思います!!
最近ブレイキンを始めた人からは想像もつかないかとは思いますが、真面目な話、現代のそこそこ上手いBboy、Bgirlが今のスキルを持ったまま2000年以前にタイムスリップができるのなら、日本あるいは世界でも有名なブレイカーになれるくらいの差はあると思ってもらえれば大丈夫です!! それくらいレベルが上がっています!!
日本のブレイキンシーンも例に漏れず、例えばパワームーブで言えば、2000年以前はエアートラックスを抜けるBboyは全国的にもまだまだそれほどおらず、連発するBboyともなれば数えられる程しかいませんでした。
そのため、バトルにおいてエアートラックスは単発であっても「必殺技」のような扱いとなっており、一発で戦況をひっくり返せるような大技として見られていました。単純なAトラックスやヘッドスピンをするだけでも、十分に観客を沸かせることができていたような時代でした。
当然、ワンハンドエアーやワープの他、今では基本の技の1つとなっているタップミル(エッグロール)といったものですら当時は存在すらしていませんでした。(海外の先進的なBboyはやっていた可能性はありますが)
今では、若手の上手いBboyであれば、基本のパワームーブの1つとしてエアートラックスを標準装備しつつありますが、当時のBboyからすればエアートラックスは特別な人しかできない技で、自分もいつかはできるようになりたい、という憧れの技となっていました!!
パワームーブの進化は未だに続いており、最近では台湾のMonkey kingがダブルエアーを成功させたり、ロシアのMalishが2000を70周以上達成、中国のBgirlがエアートラックスを150連発以上するなど、留まるところを知りません。。
この先20年後には、更にとんでもないことになっている可能性もありますね!!
また、パワームーブ以外にも目を当てると、縦系であれば、まだワンハンドラビットを確立しているBboyはほぼおらず、ラビットと言えば両手というのが基本でした。今では、足抜きや変形などのバリエーションも数多く見られますが、当時では考えられない程の進化を見せているかと思います!!
その他、軟体系やスレッド系のBboyも同様に、この20年~30年の間に信じられないほどに激的に進化をしています!!
(スレッドという言葉自体も国内にはまだ存在していなかったのではないかと思います)
その3:オールラウンダーの増加

現代のブレイキンシーンを見ると、パワームーブができて、フットワークやフロアムーブもできて、トップロックもできて、アクロバットもできて、なんならそこに、ストロングや軟体、スレッドなどの動きもできる、いわゆるオールラウンダーなBboy、Bgirlが徐々に増えてきているように思います!!
2000年以前の日本のブレイキンシーンでは、ブレイクダンスを始めると、自分はパワームーバーとしてやっていくのかスタイラーとしてやっていくのかを2択の中から選んで自分のダンススタイルを決めていくような暗黙の文化があったように感じます。
というよりも、ほぼほぼこの2択以外の考え方が当時はあまりなかったのではないかと思います。
(そんなことはない、と言われる方もいらっしゃるかもしれませんが。)
もしくは、ブレイクダンスをやりたいと思うきっかけとなることが多い「ウインドミル」や、次に習得しようとすることが多い「トーマス」に挑戦した結果によって、自然と自分のダンススタイルを決めていっていたような時代だったようにも思います。
ウインドミルやトーマスを見事できるようになり、その魅力に取りつかれた人は連発の練習やつなぎの練習を始めてそのままパワームーバーの道へ進み、習得できなかった、または習得はしたものの単発で満足して、並行して練習していたフットワークの練習に比重を置くようになった人はそのままスタイラーに、といった具合です。
どちらが良いとか、悪いとかいう話ではありませんが、バトルで勝ち上がるためには、自身の動きのバリエーションが多い方が有利になることが多いため、自然と何でもできることがバトルシーンにおいては求められるようになってきた結果、近年のオールラウンダーの増加につながっているのだと思います。
もちろん今でも、パワームーブ、スタイル(フットワーク+トップロック)、ヘッドスピン、縦系、など、特定のムーブに特化して、突き詰めているブレイカーもいるにはいますが、昔と比べればかなり減ってきている印象を受けます。
その4:Bgirl人口の増加

2000年以前は、ブレイカーと言えば圧倒的にBboyが多い時代でした。もちろんBgirlもいるにはいたのですが、今と比較すると人数はかなり少なく、感覚的には1つの練習場所に1人いるかどうかといったような状況だったのではないかと思います。(もちろん地域差などはあるかと思いますが)
そのため、今では当たり前のように行われている「Bgirlバトル」というものは、ほとんど行われておらず、BgirlはBboyに混ざってバトルをすることが一般的でした。
当然、筋力などの面で勝ることが多いBboyの方が有利になることが多く、当時のBgirlがバトルで勝ち上がるというのは、いかに過酷な環境だったかというのは想像に難くないと思います。
今では、Bgirlの人口も日本ではキッズを中心に増えているため、Bgirlバトルというカテゴリーも定着し、一般的に行われるようになっています。
また、先日のパリオリンピックでは日本のAmiが見事優勝、金メダルを獲得したことによって、今後さらにブレイキンをやりたいと思う女子が増えていくのではないでしょうか。
その5:ブレイカーの年齢層拡大

現在、Bboy・Bgirlの年齢層というのは、非常に幅が広くなってきており、下は3歳、4歳くらいから上は70代くらいまでに拡大してきていると思われます。極端な外れ値は度外視したとしても、小学生低学年くらいから、40代くらいまではかなりの数のBboy・Bgirlがいるのではないかと思われます。
2000年以前は、そもそもブレイキンの認知度がまだあまり高くなかったことや日本に入ってきてそれほど年数も経過していなかったこともあり、Bboy・Bgirl人口自体も少なく、年齢層も多くは10代後半~20代後半までとなっていたように感じます。感覚的には、大学のサークルで始める人が多く、その後、20代で就職や結婚、子供が産まれたり、転勤などによって辞めていってしまう人が多かったのではないかと思います。そのため、10歳未満、30代以上のBboy・Bgirlは、当時はかなり稀有な存在だったと言えるでしょう。
当時では数少ないキッズからブレイキンを始めてずっと続けていたブレイカーの代表がTaisukeやToshikiであり、日本を牽引するBboyとなっていきました。
また、20代後半で辞めていくブレイカーが多い中、それでもずっと続けてきたブレイカーの代表がKazuhiroやKosuke、Narumiなどであり、レジェンドと言われるような存在となっています。
今では、キッズBboy・Bgirlも非常に増えてきているため、将来的にはTaisukeやToshiki級のBboy・Bgirlがゴロゴロと出てくる可能性は大いにあり、ブレイキンシーンのスキルの底上げが図られるであろうことが予測されます。事実、既に超絶ハイスキルを持ったキッズBboy・Bgirlはゴロゴロいます。(ただ、同時に大学のサークルから始めるとなると、キッズから続けている人との差は、まるで大人と赤ん坊のような歴然とした差があり、勝負にこだわりたい人であれば、参入障壁はかなり高くなってきているかと思われます。)
そして、2023年のRed Bull BC One World Finalでは39歳のHongtenが3度目の優勝を果たしましたが、日本でも世界でもトップレベルの実力を持ち、第一線で活躍するBboy・Bgirlには30代も多く含まれるため、30代以降でも十分に活躍するブレイカーは今後も増えてくるのではないかと思われます。
事実、今年開催されたパリオリンピックの各国の代表選手には30歳超えの選手が何人もいました。日本代表のAyumiは40歳を超えてもなお素晴らしいパフォーマンスを見せ、今でも現役で世界のBgirlのトップ選手として世界中で活躍しています。
その6:練習方法の変化

練習方法も大きく変わってきています。以前は、練習をしようと思っても、そもそも知識を得ること自体が困難でした。どんな技や動きがあるのかについても、数少ないブレイキンをやっている人達のつながりの中で、こんなステップ、フリーズ、パワームーブがあるらしい、というところから始まり、その技や動きの存在がわかったところで、今度はやり方がわからない、となります。当時はまだYoutubeやSNSが今と比べるとほぼないに等しい状態だったため、映像で見れるものと言えば、数少ないVHSや僅かに出始めていたDVDくらいのものでした。
そのため、基本的には見様見真似でまずはやってみる、既にできる人にやり方の教えを乞う、以外には習得する方法がありませんでした。見様見真似でやっても、当然すぐにできるわけはなく、少しずつ「タイミングをずらしてみる」「角度を変えてみる」など、ああでもない、こうでもないと試行錯誤を何度も何度も繰り返しながらになるので、1つの技や動きができるようになるまでに何ヶ月、場合によっては何年もかかっていました。また、「見様見真似」の弊害として、パワームーブなどを練習する際に、正しいやり方ではなく自己流のやり方になってしまうこともよくあり、変な動きのクセがついてしまうということも少なくありませんでした。
スクールも多く開かれ、YoutubeやSNSでレクチャー動画がいくらでも視聴できる現在と比べると、なんて非効率的だったのだろうと思ってしまいますね。。
その7:練習場所の変化

練習場所にも変化が見られ始めているかと思います。2000年以前~2000年代にかけての練習場所は、「ストリートダンス」の名の通り、駅や路上、ガラスで自身の姿が映るビルの周辺など、「ストリート」が練習場所の中心となっていました。
それに加えて、一部、大学のサークルに所属していたBboy・Bgirlは大学の空き場所、まだあまり多くはありませんでしたがダンススタジオの関係者(経営者、インストラクター、レッスン生)はスタジオ、その他、公共施設の自由教室や体育館などといった室内はチラホラといった具合だったかと思います。
上記のように、練習場所の中心は室内よりも屋外となっていました。
(特に、それなりに環境の良い駅には、だいたい数人のBboyが集まって練習していたように思います)
屋外の練習場所はというと、色々と厳しい面がありました。まずは床の問題です。かなり汚れていたり、打ちっぱなしのコンクリートやアスファルト、レンガ、タイルなど様々で、場所によって技の制約がかなりありました。特に摩擦の大きい床や溝やスジがある床、小石などが落ちている床などでは、とてもじゃありませんがAトラックスなんてできたものではありません。練習をしないので(できないので)、当然その技が上達することはありません。ムリに練習をして頭が切れて流血していた人も見かけたことがありました。。
また、劣悪なのは床だけではありません。夏は蒸し暑い中、汗を滝のように流しながら練習し、冬は極寒の中、かじかむ手を冷たい床に着いて練習しなければいけませんでした。春や秋は花粉症の人にとっては地獄でしかありません。運動をするため大量に呼吸をすることとなり、同時に大量の花粉を体内に取り入れてしまうのです。目や喉のかゆみ、くしゃみ、鼻水と戦いながらとなるため練習どころではありませんでした。
そして、近隣住民や通行人の苦情により、警察を呼ばれたり、駅員や警備員に注意をされ、突然練習を中断せざるを得ないということも珍しくありませんでした。場合によっては、酔っぱらいのおじさんや地元のヤンキーに絡まれるなんてこともあり、常に何かしらのハプニングが起きる可能性と隣り合わせの状況での練習となっていました。
(逆に、声援を送ってもらえたり、お金をいただけるなんていう良いことも稀にありましたが)
それだけではありません。今ではあまり想像できないかもしれませんが、地域や場所によっては屋外の練習場所が、その地域のBboy達の「縄張り」のようにもなっていました。知らないBboyがその場所で勝手に練習をしていると、「誰に許可を得てここで練習しているんだ」と一触即発の状態になることもしばしば見受けられました。来た時に、最初に挨拶をきちんとして許可を得て練習するか、事前にその練習場所のBboyに話を通しておき、「●●の紹介で」などと言わなければいけないといった暗黙のルールのようなものが存在していたように思います。
今でも屋外の練習場所は存在はしていますが、近隣住民や通行人の苦情により、禁止される場所も多くなってきています。
一方で、ダンススタジオが増えたことや、年齢層が拡大したことを受けて、練習場所は屋外中心から屋内中心に変わってきています。最近では、自宅の部屋で練習できるようにしているBboy、Bgirlも増えてきています。
屋内の練習場所は、非常に快適であり、適度に滑る良い床で、冷暖房完備、花粉に悩まされることもなく、注意を受けることも、誰かに絡まれることもありません!!
最近のダンサーは間違いなく、以前よりも良い環境で練習ができていると言えるでしょう!!
その8:イベントの変化

バトルやショーケースが行われるイベントについても変わってきています。
まずはイベントが開催される時間帯です。今では、日中に行われるデイイベントが中心になっているかと思いますが、2000年以前~2000年代にかけてのイベントは、健全な時間帯に開催されるデイイベントもあるにはありましたが、まだまだ夜のイベントが多かった気がします。中には夜の12時頃から開始して、朝までのイベントというのも普通にあったように思います。
夜型のイベントから昼型のイベントが多くなった理由には、前述したBboy、Bgirl人口の増加や年齢層の拡大も影響しているかと思います。(Kidsは夜のイベントには参加できないなどの制限がかかってしまうため)
次にイベントが開催される場所です。最近のイベントが開催される場所は、ダンススタジオや公共の施設、オープンな野外施設など、こちらも健全な場所が多いイメージです。しかしながら、2000年以前~2000年代にかけてのイベントとなると開催される時間帯との関係性もありますが、その場所はクラブやバー、ライブハウスなど比較的アンダーグラウンドな場所で開催されることが多かったように思います。そのため、2000年以前~2000年代にかけてのBboy、Bgirlは世間からも「不良」っぽい印象を持たれることも多かったのかもしれません。
また、場所が場所ということもあり、不要なトラブルに巻き込まれるということもチラホラ耳にしたりすることもありました。
また、イベントの規模や数に目を向けると、2000年以前では、まだまだ世界的なブレイキンのイベントはそれほど多くなく、有名なもので言えば、Battle of the Year、UK Bboy Championship、Free Style Session、IBEなど、両手で収まる程度だったのではないかと思います。それから、2004年にRed Bull BC Oneが初開催されたのを皮切りに次々と世界規模の大会が増えていき、今では数えきれない程になっています。
卵が先か鶏が先かは分かりませんが、こうした大きなイベントが数多く増えたことにより、Bboy、Bgirl人口は増え、ブレイキンシーンが世界的に盛り上がってきていることに良い影響を与えているのは事実かと思います。

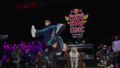
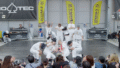
コメント